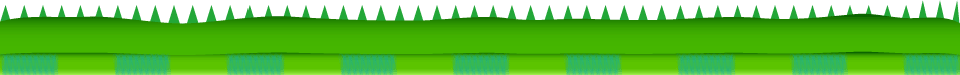چ©’ژٹظ‚جچإ‹ك‚جƒCƒxƒ“ƒg‚âڈî•ٌ‚ب‚ا‚ً‚¨’m‚点‚µ‚ـ‚·پB |
پ@پœ 2025”NپuڈH‚جپI’ژ‚ً‚آ‚©‚ـ‚¦‚ؤ‚ف‚é‚©‚¢پIپv‚ھٹJچأ‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پI |
پ@2025”N‚XŒژ2‚V“ْپAڈdˆن–ٍ—pگA•¨‰€‚ئ‚ج‹¤چأ‚إپA‘q•~چ©’ژ“¯چD‰ï‚جƒgƒ“ƒ{‚ةڈع‚µ‚¢ژçˆہ“ض‚³‚ٌ‚ًچuژt‚ة‚¨Œ}‚¦‚µ‚ؤٹJچأ‚¢‚½‚µ‚ـ‚µ‚½پB “V‹C‚ة‚حŒb‚ـ‚ê‚ـ‚µ‚½‚ھپA–زڈ‹‚ج‚¹‚¢‚©”ًڈ‹‚ةڈoŒü‚¢‚ؤ‚¢‚½ƒAƒJƒlپiƒAƒJƒgƒ“ƒ{—قپj‚جژp‚ھ‚ ‚ـ‚茩‚ç‚ê‚ب‚©‚ء‚½‚ب‚اپA—ل”N‚ئ”ن‚ׂؤ’ژ‚جگ”‚âژي—ق‚حڈ‚ب‚©‚ء‚½‚و‚¤‚إ‚µ‚½پB‚ـ‚½پAƒLƒٹƒMƒٹƒX—ق‚جژ¨‚âŒممہ‚ج–ح—l‚ب‚اچׂ©‚¢‚ئ‚±‚ë‚ـ‚إٹدژ@‚µ‚ـ‚µ‚½پBچإ‹كŒ§“à‚ة‚àŒ©‚ç‚ê‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚½“ى•ûŒn‚جƒAƒJƒnƒlƒIƒ“ƒuƒoƒbƒ^‚àŒممہ‚ًٹg‚°‚ؤŒ©‚آ‚¯‚½ژq‚ا‚à‚à‚¢‚½‚و‚¤‚إ‚·پB
 |
 |
‰·ژ؛ƒGƒٹƒA‚ج’r‚إƒgƒ“ƒ{‚ً•ك‚ـ‚¦‚ؤ‚ف‚و‚¤ |
“ى•ûŒn‚جƒAƒJƒnƒlƒIƒ“ƒuƒoƒbƒ^‚ھگA•¨‰€‚ة’è’…پHپI |
 |
 |
ژ¼’n‚ج–ط“¹‚©‚ç’ژ‚ً’T‚µ‚ـ‚· |
—ر‰ڈ‚ج‘گ‚ق‚ç‚إƒoƒbƒ^’T‚µ |
 |

|
| ƒRƒJƒ}ƒLƒٹ‚ًƒQƒbƒg |
چإŒم‚ج‚ـ‚ئ‚ك‚إ‚· |
|
پœ 2025”Nپu‰ؤ‚جپI’ژ‚ً‚آ‚©‚ـ‚¦‚ؤ ‚ف‚é ‚©‚¢پIپv‚ھٹJچأ‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پI |
2025”N8Œژ16“ْپi“yپjپA‰J“V‚ج‚½‚ك‰„ٹْ‚³‚ê‚ؤٹJچأ‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پB
چuژt‚ةƒgƒ“ƒ{‚جگوگ¶‚±‚ئ‘q•~چ©’ژ“¯چD‰ï‚جژçˆہ“ض‚³‚ٌ‚ًŒ}‚¦پA‚ـ‚½ڈdˆن–ٍ—pگA•¨‰€‚©‚ç‚à•ذ‰ھ‰€’·‚ئƒ{ƒ‰ƒ“ƒeƒBƒA‚ج•û‚ھژQ‰ءپB’·ˆّ‚ڈ‹‚³‚ئٹ£‘‡‚ج‚½‚ك’ژ‚جژي—ق‚âگ”‚àڈ‚ب‚©‚ء‚½‚ج‚إ‚·‚ھپA“ْ‚²‚ë‚ ‚ـ‚茩‚©‚¯‚ب‚¢ƒ`ƒ‡ƒEƒgƒ“ƒ{‚⃄ƒuƒ„ƒ“ƒ}‚ب‚اپA‚ ‚é’ِ“x‚جژي—ق‚ھچجڈW‚إ‚«‚ؤ–‘«پB ‚؟‚¢‚³‚بژq‚ا‚à‚à‘½‚پAژ©‘R‚ئگG‚êچ‡‚¤‹@‰ï‚ًچى‚ç‚ꂽ•غŒىژز‚ج•û‚ة‚àٹ´ژس‚إ‚·پB پ¦ژتگ^‚ح•ذ‰ھ‰€’·ژB‰e
|
پ@پœ 2025”Nپu‚ف‚ٌ‚ب‚إ‚½‚ٌ‚¯‚ٌپI–é‚جچ©’ژٹدژ@‰ïپv‚ھٹJچأ‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پI |
پ@2025”N7Œژ26“ْپi“yپj‚حڈdˆن–ٍ—pگA•¨‰€‚ئ‚ج‹¤چأ‚إپu ‚ف‚ٌ‚ب‚إ‚½‚ٌ‚¯‚ٌپI–é‚جچ©’ژٹدژ@‰ïپv‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پBچ،”N‚ح‚ا‚ٌ‚ب’ژ‚ھŒ©‚ç‚ꂽ‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB
 |
 |
ٹJ‰ï‚إ‚·پB’چˆسژ–چ€‚â“ْ’ِگà–¾پAچuژtڈذ‰î‚ب‚ا‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB‚¾‚ٌ‚¾‚ٌ”–ˆأ‚‚ب‚ء‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پB |
ƒ‰ƒCƒgƒgƒ‰ƒbƒv‚»‚ج‚PپD–h’ژ“”پiƒIƒŒƒ“ƒWپE“چ”¨‚جٹQ’ژ‘خچôپj‚ج‘¤‚إ‚جƒgƒ‰ƒbƒv‚ج‚¹‚¢‚©’ژ‚حڈ‚ب‚¢‚و‚¤‚إ‚·پB |
 |
 |
ƒ‰ƒCƒgƒgƒ‰ƒbƒv‚»‚ج‚QپD—ر‚ج’†‚جƒgƒ‰ƒbƒv‚ة‚حƒsƒJƒsƒJ‚جƒRƒKƒlƒ€ƒV‚ج’‡ٹش‚ھ‚½‚‚³‚ٌپB‰é‚ج’‡ٹش‚à‚½‚‚³‚ٌپBƒNƒڈƒKƒ^—ق‚ًŒ©‚آ‚¯‚½•û‚àپB |
‚±‚جچsژ–‚ج’è”شپAچ،”N‚àƒAƒuƒ‰ƒ[ƒ~‚ج‰H‰»‚ھŒ©‚ç‚ê‚ـ‚µ‚½پBٹk‚©‚çڈo‚ؤ”’‚¢‰H‚ھگL‚ر‚é‚ـ‚إٹدژ@‚إ‚«‚ـ‚µ‚½پB |
 |
ڈdˆن–ٍ—pگA•¨‰€‚إ‚حپA2021”N‚ةچ©’ژگ¶‘§’²چ¸‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½‚ھپA‚±‚جچsژ–‚إŒ©‚آ‚©‚ء‚½چ¶‚ج3ژي‚ح‰€“à‚إ‚حڈ‰‚ك‚ؤ‚ج‹Lک^‚إ‚µ‚½پB |
|
پ@پœ 2025”N‚جٹ±ژxپA2025”N‚جٹ±ژx‚إ‚ ‚éپA–¤پiژضپj‚ة‚؟‚ب‚ٌ‚¾چ©’ژڈذ‰î(2024/12/24پj |
پ@2025”N‚ح–¤”NپBژض‚ة‚؟‚ب‚ٌ‚¾چ©’ژ‚جڈذ‰îƒpƒlƒ‹‚ً“Wژ¦ژ؛‚ةگف’u‚µ‚ـ‚µ‚½پB
|
پ@پœ 2024”N پu‰ؤ‚ج’ژ ‚ًپI‚آ‚©‚ـ‚¦‚ؤ‚ف‚é ‚©‚¢پIپv‚ھٹJچأ‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پI |
پ@2024”N8Œژ12“ْ(ŒژپFڈj“ْ)پu‰ؤ‚جپI’ژ‚ً‚آ‚©‚ـ‚¦‚ؤ‚ف‚é‚©‚¢پIپv
پ@ڈdˆن–ٍ—pگA•¨‰€‚ئ‚ج‹¤چأچsژ–
پ@
ڈ‹‚³‚ً”ً‚¯‘پ’©‚و‚èپi8:00‚©‚ç10پF00پjٹJچأ‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پB“VŒَ‚à‘fگ°‚炵‚پA‰“‚‚حچپگىŒ§‚ج‰ئ‘°‚àٹـ‚كپA50–¼ژم‚جژQ‰ءژز‚إ‚µ‚½پB ‘q•~چ©’ژ“¯چD‰ï‚و‚èƒgƒ“ƒ{‚ةڈع‚µ‚¢ژçˆہ“ض‚³‚ٌ‚ة—ˆ‚ؤ‚¢‚½‚¾‚«‚ـ‚µ‚½پB
پ@چ،”N‚ح“ء‚ة’ژ‚½‚؟‚جژp‚ھڈ‚ب‚¢‚و‚¤‚إ‚µ‚½‚ھپA’r‚ج‚ظ‚ئ‚èپA‘گ‚ق‚çپAژ¼’nپA—ر‚ج’†‚إگeژq‚ھ—\‘zˆبڈم‚جژي—ق‚ج’ژ‚½‚؟‚ًٹدژ@‚µ‚½‚è•ك‚ـ‚¦‚½‚肵‚ب‚ھ‚çپA–ٌ2ژٹش‚ً‰ك‚²‚µ‚ـ‚µ‚½پBگl‹C‚جƒNƒڈƒKƒ^‚âƒJƒ}ƒLƒٹ‚ب‚ا‚à•ك‚ـ‚¦‚½ژq‚ا‚à‚à‚¢‚ـ‚µ‚½پB
ژ÷‰t‚ةڈW‚ـ‚éƒIƒIƒXƒYƒپƒoƒ`‚ً‰“–ع‚ةٹدژ@‚·‚邱‚ئ‚à‚إ‚«‚ـ‚µ‚½پB
 |
 |
’©‘پ‚ڈWچ‡پA‚³‚ء‚»‚پu’r‚ج‚ظ‚ئ‚è‚إƒgƒ“ƒ{‚ئ‚è‚إ‚· |
”²‚¯‚é‚و‚¤‚بگآ‹َ‚ج‚à‚ئƒoƒbƒ^—ق‚ً•ك‚ـ‚¦‚ـ‚µ‚½ |
 |
 |
ژ¼’nƒGƒٹƒA‚إ‚ج—رٹش‚إ‚à’ژ’T‚µ |
چsژ–چإŒم‚ة–ط‰A‚ةڈW‚ـ‚èگ¬‰ت‚ج”•\پB‚ا‚ٌ‚ب’ژ‚ھ‚ئ‚ꂽ‚©‚ـ‚ئ‚ك‚ً‚µ‚ـ‚µ‚½ |
|
پ@پœ 2023”NپuڈH‚جپIپ@’ژ‚ً‚آ‚©‚ـ‚¦‚ؤ‚ف‚éپ@‚©‚¢پIپv‚ھٹJچأ‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پI |
پ@
پ@2023”N9Œژ23“ْپi“yپjپuڈH‚جپIپ@’ژ‚ً‚آ‚©‚ـ‚¦‚ؤ‚ف‚éپ@‚©‚¢پIپv(ڈdˆن–ٍ—pگA•¨‰€‚ئ‚ج‹¤چأپj
پ@ڈêڈٹپFڈdˆن–ٍ—pگA•¨‰€“à
پ@
‚¢‚آ‚à‚ب‚ھ‚ç‚جگ·‹µ‚إچً”N“¯—l50–¼‚ظ‚ا‚جژQ‰ءژز‚©پAƒoƒbƒ^پAƒRƒIƒچƒMپAƒJƒ}ƒLƒٹپAƒgƒ“ƒ{‚ب‚ا‘½‚‚جچ©’ژ‚ًŒ©‚آ‚¯‚ؤ‚حچج‚èپAٹدژ@‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پBچ،”N‚حژcڈ‹‚ھŒµ‚µ‚©‚ء‚½‚¹‚¢‚©,‰ؤ‚جٹشژRٹش•”‚ض”ًڈ‹‚ةچs‚ء‚ؤ‚¢‚éƒAƒJƒl—قپiƒAƒJƒgƒ“ƒ{پj‚ح‚ ‚ـ‚蕽–ى‚ة‹A‚ء‚ؤ‚«‚ؤ‚¢‚ـ‚¹‚ٌ‚إ‚µ‚½‚ج‚إپAڈ‚ب‚¢‚و‚¤‚ةژv‚¢‚ـ‚µ‚½پB
|
پœ پuٹOچ‘‚جچ©’ژگطژèپvپu“ْ–{‚جگطژè‚ة“oڈê‚·‚éچ©’ژپv‚ج“Wژ¦‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پ@پi2023/‚T/16پj |
گV“Wژ¦‚ج‚²ڈذ‰î‚إ‚·پB گطژè‚جƒfƒUƒCƒ“‚ةچ©’ژ‚ھ‚ ‚é‚à‚ج‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·‚ثپB ‚»‚ê‚ًڈW‚ك‚ؤ•W–{‚ئ‹¤‚ة‚²ڈذ‰î‚·‚é“Wژ¦” ‚âƒpƒlƒ‹‚ًچى‚è‚ـ‚µ‚½پB “ْ–{‚ج‰ù‚©‚µ‚¢گطژèپAٹCٹO‚ج‚¨چ‘•؟‚ھ‚و‚•ھ‚©‚é‘fگ°‚炵‚¢ƒfƒUƒCƒ“گطژè‚ب‚اپAˆêŒ©‚ج‰؟’l‚ ‚è‚إ‚·پB‚¨‰z‚µ‚جچغ‚ة‚ح‚؛‚ذ‚²——‚‚¾‚³‚¢پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
|
پœ چ©’ژ•W–{‚ج‘فڈo‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚· |
پ@‘q•~چ©’ژٹظ‚إ‚حپA•W–{‚ج‘فڈo‚à‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@‘q•~چ©’ژٹظ‚جڈٹ‘ •W–{‚ج‚ب‚©‚إپAƒfپ[ƒ^‚ھ‚ب‚¢‚à‚ج‚ب‚ا•W–{‚ئ‚µ‚ؤ‚حژg‚¦‚ب‚¢‚à‚ج‚ًڈW‚ك‚ؤ‘ف‚µڈo‚µ—p‚ج•W–{” ‚ًچى‚è‚ـ‚µ‚½پBŒ»چف‚حƒ`ƒ‡ƒE—قپEƒJƒ~ƒLƒٹƒ€ƒV—قپEچb’ژ—قپEƒoƒbƒ^—قپEƒgƒ“ƒ{—ق‚ب‚اڈ‚µ‚¸‚آ•ہ‚ׂ½‚à‚ج‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB‚±‚ê‚©‚ç‚àƒoƒbƒ^‚ب‚اژي—ق‚ً‘‚₵‚ؤ‚¢‚—\’è‚ة‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚³‚ء‚»‚پA2020”N6Œژ‚ة‚ح‘q•~ژs“à‚ج•غˆç‰€‚©‚ç5” ‘فڈoٹَ–]‚ھ‚ ‚èپA‰€ژ™‚½‚؟‚ة‚ةŒ©‚ؤ‚¢‚½‚¾‚‹@‰ï‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB
پ@‚²‹»–،‚ج‚ ‚é•ûپA‘فڈo‚²—v–]‚ج•û‚حپA‘q•~چ©’ژٹظ‚ـ‚إ‚²کA—چپ•‚²‘ٹ’k‚‚¾‚³‚¢پB
پ@پ@پ@پ@پ@ |
‘ف‚µڈo‚µ—pپ@چ©’ژ•W–{‚ج—ل |
|
پœ پu‰ھژRŒ§‚جƒŒƒbƒhƒٹƒXƒgچ©’ژپv“Wژ¦چXگV‚ة‚آ‚¢‚ؤ |
| پ@
پ@چ،‰ٌ‚جپu‰ھژRŒ§ƒŒƒbƒhƒfپ[ƒ^ƒuƒbƒN2020پiˆب‰؛RDB2020‚ئ—ھپjپv‚جچإ‘ه‚ج“ء’¥‚حپA‘O‰ٌ‚جپu‰ھژRŒ§ƒŒƒbƒhƒfپ[ƒ^ƒuƒbƒN2009پiˆب‰؛RDB2009‚ئ—ھپjپv‚ئ”نٹr‚µ‚ؤ‘خڈغ‚ئ‚ب‚éچ©’ژ‚ھ172ژي‚©‚ç265ژي‚ئ–ٌ1.5”{‚ة‚à‚ب‚ء‚½‚±‚ئ‚إ‚·پBژc”O‚ب‚ھ‚çگV‚½‚ة‚Rژي‚ھپuگâ–إپv‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¢‚ـ‚µ‚½پBˆب‰؛پAپuگâ–إٹ뜜‡T—قپv‚ھپ{13ژيپAپuگâ–إٹ뜜‡U—قپv‚ھپ{31ژي‚ئ‚¢‚¤‚و‚¤‚ة‘ه•‚ة‘‰ء‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBپu—¯ˆسپv‚ج‚ف‚ھپ|34ژي‚إ‚·‚ھپA‚±‚ê‚حڈمˆت‚جƒJƒeƒSƒٹپ[‚ةˆعچs‚µ‚ؤ‚¢‚ء‚½‚½‚ك‚إ‚ ‚èپAŒˆ‚µ‚ؤچD“]‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ي‚¯‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB
پ@ ‚±‚ê‚瑉ء‚µ‚½ژي‚ً•ھگح‚µ‚ؤ‚ف‚ـ‚·‚ئپA‘گŒ´گ«چ©’ژ‚ئگ…گ¶چ©’ژ‚ھ‘ه•د–ع—§‚؟‚ـ‚·پB—ل‚¦‚خچ،‰ٌپuگâ–إپv‚ئ‚ب‚ء‚½ƒ`ƒ‡ƒE‚Qژي‚ح‘گŒ´گ«‚ج‚à‚ج‚إ‚ ‚èپA‘¼‚جچ©’ژ‚إ‚à‚±‚جŒXŒü‚ھŒ©‚ç‚ê‚ـ‚·پBگ…گ¶چ©’ژ‚إ‚حپAƒQƒ“ƒSƒچƒE‚ج’‡ٹش‚ھRDB2009‚ج‚Wژي‚©‚çپARDB2020‚إ‚حˆê‹C‚ة21ژي‚ة‘‰ء‚µ‚ـ‚µ‚½پBگ…•س‚ًگ¶ٹˆ‚جڈê‚ئ‚·‚éƒgƒ“ƒ{‚ج’‡ٹش‚à“¯—l‚إ‚·پB‚±‚ج‘گŒ´‚ئگ…•س‚ئ‚¢‚¤‚Q‚آ‚جٹآ‹«‚حگ[‚¢ژR‚ج’†‚ة‚إ‚ح‚ب‚پAگg‹ك‚ب—¢ژR‚ة‚ ‚é‚à‚ج‚إ‚·پB—¢ژR‚ج•ِ‰َ‚ھگi‚ق‚ة‚آ‚êچ©’ژ‚جگ¶‘§ٹآ‹«‚ح‚ـ‚·‚ـ‚·ˆ«‰»‚µپAچ،ŒمRDB‘خڈغ‚جچ©’ژ‚ھ‚³‚ç‚ة‘‚¦‚ؤ‚¢‚‚ج‚إ‚ح‚ئŒœ”O‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@
چ،‰ٌ‚جRDB2020‚ج”چs‚ًژَ‚¯‚ؤپA‘q•~چ©’ژٹظ‚إ‚ح‚±‚جƒRپ[ƒiپ[‚ج“Wژ¦‚ًگV‚µ‚‚µ‚ـ‚µ‚½پB‚µ‚©‚µ“Wژ¦ƒXƒyپ[ƒX‚©‚çپAچإ‘ه‚إ‚à95ژي’ِ“x‚ھŒہٹE‚إ‚·پB
‚»‚±‚إپ@پœپuگâ–إپv‚ئپuگâ–إٹ뜜‡T—قپv‚ح“–ٹظ‚ة•W–{‚ھ‚ ‚éŒہ‚è‚·‚ׂؤ‚ً“Wژ¦
پ@پ@پ@ پ@پœپuگâ–إٹ뜜‡U—قپv‚ئپuڈ€گâ–إٹ뜜پv‚حˆê”ت‚ج•û‚ة‚à‚و‚’m‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é‚à‚ج‚ً‘I’èپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiƒ^ƒKƒپ‚âƒnƒbƒ`ƒ‡ƒEƒgƒ“ƒ{‚ب‚اپj
پ@پ@پ@ پ@پœپuڈî•ٌ•s‘«پv‚ئپu—¯ˆسپv‚جƒJƒeƒSƒٹپ[‚جژي‚حژc”O‚إ‚·‚ھ“Wژ¦‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚¹‚ٌپB
پ@‚ب‚¨ŒآپX‚جچ©’ژ‚جڈذ‰î‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAچ،Œم‘q•~چ©’ژٹظFB‚ةŒfچع‚µ‚ؤ‚¢‚«‚ـ‚·‚ج‚إپA‚؛‚ذ‚²——‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB
پ@‚±‚ê‚ç‚ج“Wژ¦‚ً’ت‚¶‚ؤ—ˆٹظژز‚جٹF—l‚ج‚²—‰ً‚ھگ[‚ـ‚èپA‰ھژRŒ§‚جچ©’ژ‚ج•غŒى‚ة‚آ‚ب‚ھ‚ء‚ؤ‚¢‚¯‚خ‚ئٹè‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
 پ@‰ھژRŒ§”إƒŒƒbƒhƒfپ[ƒ^ƒuƒbƒN2020 پ@‰ھژRŒ§”إƒŒƒbƒhƒfپ[ƒ^ƒuƒbƒN2020
|
| |