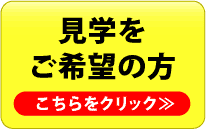おかやまの植物事典
ナンバンギセル(ハマウツボ科) Aeginetia indica
 |
 |
| ▲夏~秋ごろ、花茎の先に淡紫色の花を1つ咲かせる。やや下向きにうつむいて咲く花を物思いにふける姿に例えて、古くは「思い草」と呼んだ。 | ▲タバコを吸うためのキセル(煙管)に似ているので「南蛮煙管」。茎に見える部分は花茎で、本当の茎は根元の部分であり、鱗片状に退化した葉がある。 |
ナンバンギセルは、日本全土および中国、東南アジアからインドまで広く分布するハマウツボ科の一年草です。旧来の植物の分類体系では、日本に分布するハマウツボ科の植物はナンバンギセル属のほか、ハマウツボ属、オニク属、キヨスミウツボ属の4属およそ6種とされていましたが、近年の遺伝子解析による研究結果を反映した新しい分類体系(APGⅢ)では、ママコナ属、コゴメグサ属、ヒキヨモギ属などゴマノハグサ科の一部がハマウツボ科として扱われるようになっていますので、新旧の分類体系により、ハマウツボ科に属するとされる植物の種類はずいぶんと異なります。しかし、新旧の分類体系を問わず、ハマウツボ科の植物は、そのほとんどが一生のうち一時期あるいは全期間を他の植物に寄生して養分や水分を得る、寄生植物であることに特徴があります。本種は、発芽直後からススキやミョウガ、あるいはサトウキビなどの根に寄生して成長し、開花まで行う「全寄生植物」であるため、光合成を行って自分で養分を作り出す必要がないため光合成色素を持っていません(全寄生植物に対して、光合成色素を持ち、自分でも光合成を行って養分を得ることができる寄生植物を「半寄生植物」と言います)。
 |
 |
| ▲花弁を裂いて雄しべと雌しべを露出させた状態。雌しべの頭(柱頭)は非常に大きく、雄しべは花粉を出すため筒状になっている。 | ▲植物園内には白花のナンバンギセル(園芸品)も栽培している。白花といっても完全な白化品ではなく、花弁の先はわずかに紅をさしたように色づく。 |
なんとも奇妙な植物ではありますが、植物としては古くから知られていたようで、万葉集にも「道の辺の 尾花が下の思ひ草 今さらに なぞものか思はむ」と、花がやや下を向いて咲く様子を、恋に思い悩んでいる様子に例えて、「思い草」と呼んでいます。「尾花」とはススキのことですから、ススキの根元に咲く花として、万葉の時代から認識されていたことが分かります。「思い草」とは情緒ある名ですが、16~17世紀にタバコが外国より伝来した際に喫煙器具である「キセル(煙管)」も持ち込まれ、タバコとともに広まりましたが、「思い草」の姿が「キセル」そっくりであるということで、「南蛮(外国)から来た煙管(という物)に似ている花」ということで、「思い草」の名は廃れて「ナンバンギセル」の名で呼ばれるようになったようです。
本種は寄生植物であるため、光合成のための器官である葉は着いていませんが、ふつう「ナンバンギセルの茎」と言っているのは実は花の下に付いている花茎の部分で、本種の本当の茎は地中の浅い位置にあって非常に短く、退化して鱗片状になった葉がまばらについています。茎からは細い根(寄生根)を寄生先の植物の根に伸ばして同化させ、養分を吸収します。夏から秋ごろ、地上に10~30cm程度の花茎を伸ばし、その先に長さ3cmほどの筒状の淡紫色の花を1つ咲かせます。花は横向き、あるいはやや下向きに咲き、花弁の先はごく浅く5裂してやや反り返ります。花の内部には先端(柱頭)が大きく広がった1本の雌しべと4本の雄しべがあります。雄しべは筒状になっており、筒の内部から花粉が出てくるようになっています。花後は花茎と花のがくの部分はそのまま立ち枯れた状態になり、枯れた状態のがくに包まれた果実の中に多数の細かな種子ができ、乾燥するとがくごと果実が裂けて種子を地面に落とし、種子は降雨時などに土砂とともに流されるなどしながら徐々に地中に入り込み、やがて再び宿主の根に寄生します。
 |
 |
| ▲花後にはがくに包まれた状態で果実ができる。花茎は立ち枯れた状態となり、果実は乾燥するとがくの部分ごと裂け、種子を散布する。 | ▲果実の中には、非常に細かな粉状の種子がつまっている。この種子は長期間発芽せずに休眠しており、宿主の根から分泌される化学物質を感知して発芽する。 |
本種などハマウツボ科の種子は、普通に播いても発芽することはまずなく、寄生先の植物の根から分泌される化学物質を感知して発芽するとされます。この化学物質の影響のある距離は数mm程度だそうですが、本種の種子は小さいため、内部の少ない養分で根を伸ばせる距離は限られます。そこで、宿主植物の根が近くに来た時にのみ発芽し、寄生が成功する確率を高めるような仕組みになったと考えられています。本種を盆栽(鉢植え)としたものを見かけることがありますが、これはススキやチガヤなどの根に本種の種子を擦りつけて寄生させたものです。根に種子を直接付けた場合には、高い割合で寄生させることができますが、あまり寄生させすぎると、宿主植物が養分を取られすぎて弱ったり枯れてしまうことがありますので、栽培する場合は注意が必要です。野生のものでも、本種が寄生しているススキの株は秋になっても穂が出ないか、出るのが遅くなるなどの影響がみられることがあります。
当園では1980年(昭和55年)に園内のススキに県内産の本種の種子を播いたものが年々増えて、現在では湿地エリアの湿地内外に生えているススキの他、イネ科のカモノハシなどの根元で8月頃から9月頃にかけて開花しているのが観察できます。温室エリアには1985年(昭和60年)ごろ、古屋野名誉園長が友人から譲り受けた関東産の白花品(完全な白化品ではなく、花弁のふちに紅が入る)の種子も播種しており、こちらは9月下旬~10月頃に見ることができます。