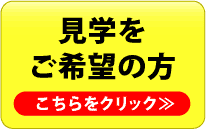おかやまの植物事典
ノカンゾウ(ワスレグサ科) Hemerocallis fulva var. disticha
 |
 |
| ▲当園では県内産のものを植栽している。やや湿った場所を好むが、植栽の場合はかなり乾燥した場所でも生育可能。 | ▲花被片は6枚、先は反り返り、6本の雄しべと1本の雌しべがある。 花筒は3~4cmあり、ヤブカンゾウなどより長い。 |
ノカンゾウは、本州から沖縄にかけての、水路ぞいや水田周辺などのやや湿り気のある草地に生育することが多い多年草です。 国外では中国および台湾に分布します。 岡山県ではおもに、ある程度の降水量がある県中部の吉備高原地域から北部の中国山地にかけて生育していますが、ヤブカンゾウ H. fulva var. kwanso に比べれば少なく、さらに近年はかなり数を減らしているようで、偶然に出会うことはほとんどなくなっています。 2025年現在、本種は環境省、岡山県ともにレッドデータ種とはされていませんが、都府県のレッドデータブック/レッドリストではレッドデータ種となっている場合も多く、岡山県においても、近い将来レッドデータ種となってもおかしくない生育状況にあると考えられます。 ちなみに母種 H. fulva var. fulva は中国原産で日本には自生しませんが、ホンカンゾウ/シナカンゾウと呼ばれ、生薬や園芸種としてしばしば栽培されています。
 |
 |
| ▲花の色は地域(集団)によって変化が多く、赤みの強いものはベニカンゾウと呼ばれることもある。 (写真:2010年7月 広島県) | ▲花は1日花だが、夕方に咲き、明け方にしぼむユウスゲとは逆で、明け方に開き、夕方にしぼむ。 |
花期は7~8月頃、高さ50~90cmほどの花茎の頂部に橙赤~赤褐色で長さ7~8cmの6枚の花被片をもつ花を咲かせます。 花被片の先は反り返り、上部に湾曲した6本の雄しべと1本の雌しべが突き出します。 花被片の下部は合着して花筒となっていますが、花筒部の長さは3~4cmと、ヤブカンゾウ(花筒の長さ2cm程度)などよりも長いことが特徴です。 花色の赤みが濃いものは「ベニカンゾウ」と呼ばれることがありますが、この名はニッコウキスゲ(ゼンテイカ) H. middendorffii var. esculenta と本種との雑種と推定されているムサシノワスレグサ(ムサシノキスゲ) H. fulva var. longituba / H. exilis の別名ともされる場合があり、混乱しやすいので注意が必要です。
花はワスレグサ属の他の種と同様、1日花ですが、夕方に咲いて明け方にしぼむユウスゲ H. citrina var. vespertina とは逆で、明け方に開花し、夕方にしぼみます。 3倍体(染色体数 2n=33)であり、結実しないヤブカンゾウとは異なり、2倍体(2n=22)ですが(大橋広好・門田裕一ほか編.2015.改訂新版 日本の野生植物1.平凡社.p.238-239)、ほとんど結実することはありません。 当園でも小さな若い果実までは観察されますが、その後は黒く干からびて落下してしまいます。
 |
 |
| ▲開花後に出来た若い果実。 2倍体で結実可能だが、ほとんど結実せず、果実はこのまま干からびて落下する。 | ▲葉は長さ50~70cm、幅1~1.5cmの線形で地際から叢生する。 主脈付近はV字型に凹み、裏面に隆起している。 |
葉は長さ50~70cm、幅1~1.5cmの線形で地際から叢生し、中央付近で折れ曲がって葉先が垂れ下がる形となります。 葉の主脈付近はV字型に凹み、裏面に隆起しています。 地下の根は淡黄色で太く、生育初期には根に紡錘形の膨らみが多く見られますが、株が大きくなると膨らみは少なくなり、長い根茎を伸ばしてその先に新株を作って増殖するようになります(当園での栽培条件下の観察による)。
 |
 |
| ▲栽培条件下の観察では、生育初期の根には紡錘形の膨らみが見られるが、株が大きくなると膨らみは減少する。 | ▲根茎を長く伸ばし、先端に新株を作って増殖する。 同属のユウスゲなどはこのような長い根茎は持たない。 |
和名は「野・萱草」で、その名の通り野に生える萱草(かんぞう)の意味です。 万葉集などには、おそらくはヤブカンゾウなどと区別されずに属の和名ともなっている「忘れ草」の名で登場します。 これは「私のことを忘れないで」というムラサキ科のワスレナグサ(勿忘草)とは逆で、この花を身に付けたり、植えたりすると辛いことを忘れられると信じられていたためですが、中でもユニークな歌が大伴家持の詠んだ「忘れ草 我が下紐に着けたれど 醜の醜草(しこのしこぐさ)言(こと)にしありけり」という歌で、「忘れ草を身に着けたが(失恋の辛さを全く忘れられなかった)、このつまらない草は名ばかりで効果がなかった」と、「忘れ草」をののしっている歌です。 実は、この歌の贈り先は、後に家持の正妻となる「大伴坂上大嬢(おおとものさかのうえのおおいらつめ)」であり、忘れ草の効果がないほど、相手への気持ちが強いことを表した歌となっています。 属の学名 Hemerocallis (ヘメロカリス)は「美しさ+1日」という意味のギリシャ語が語源で、この仲間の花が一日花であることを意味し、種小名 fulva は「濃黄色」、 変種名 disticha は「2列の/2縦列の」を意味するラテン語 distichus に由来し(豊国秀夫 編.1987.植物学ラテン語辞典.至文堂.p.69,86,94)、本種の花序が2分枝していることを意味しているものと思われます。
なお、ワスレグサ属の植物は、同属内では非常に交雑しやすいという特徴があり、人工交配によって様々な園芸品種が作出されています。 野生環境においては開花時間や分布域、生息環境の違いなどが交配機会の阻害要因となり、それぞれの種が維持されていますが、岡山県では近年、観光振興の目的で、西日本には自生しないニッコウキスゲなどを本種とともに大規模に植栽するということが行なわれている地域もあり、交雑による本種など在来種への遺伝子汚染が懸念されます。
(2025.7.12)