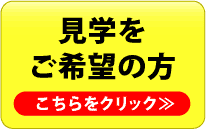おかやまの植物事典
シラガブドウ (ブドウ科) Vitis shiragae
環境省第5次レッドリスト(2025):絶滅危惧ⅠB類 / 岡山県版レッドリスト2025:留意
 |
 |
| ▲植物園内に植栽している株の様子。自然状態でも、巻きひげで絡みついて、樹木など他の植物の上を覆うように広がる。 | ▲果実は9月頃に黒色に熟し、食べられる。 ブドウの房は長さ5~12cmほどで、ブドウの房らしい比較的整った形のものが多い。 |
シラガブドウは、国内では岡山県西部を流れる高梁川流域のみに分布が知られる、落葉性の木本つる植物です。 国外では朝鮮半島南部と済州島、中国東部に分布する(大橋広好・門田裕一ほか編.2016.改訂新版 日本の野生植物2.平凡社.p.237)とされます。 以前は中国およびロシア南東部に分布するチョウセン(マンシュウ)ヤマブドウ V. amurensis と同一とする見解もありましたが、現在は、「別種とみなすべきである。」(大橋・門田ほか.2016)とされています。 全国的にはきわめて分布が限られている植物で、絶滅危惧種とされていますが、高梁川流域に限れば、上流域の新見市・高梁市から、下流は倉敷市にかけて、河川敷や川に近い林縁など日当たりのよい場所に普通とまでは言えませんが比較的多くの個体が安定して生育しているとされ、岡山県ではレッドデータ植物とはされていません。 ただ、河川の護岸工事や生育地の植生変化等により生育環境が悪化し、個体数が減少している場所もありますので、生育状況には注意しておく必要があると考えられます。
マメ科のフジ類のように茎そのもので巻きつくようなことはなく、同属の野生ブドウ類と同じく、葉と対になって出る巻きひげで樹木など他の植物に絡みつき、他の植物の上部を覆うように広がります。 若い枝には稜角があり、はじめ灰白色、のちに淡黄褐色になる綿くずのようなクモ毛が目立ちます。 枝の稜角は古い枝でも確認することができ、他の野生のブドウ属の植物との大きな区別点となります。 樹皮は他のブドウ類と同じように茶褐色で縦に長くはがれますが、幹はマスカットや巨峰などの園芸ブドウほどには太くはなりません。
 |
 |
| ▲葉は質薄く、長さ、幅ともに7~15cmほど、偏卵形あるいは偏円形で、3浅裂。 表面ははじめ毛があるが脱落して無毛となる。 | ▲葉裏ははじめ灰白色、やがて淡黄褐色になる薄いクモ毛があるが、生育環境や個体差、時期によって毛の量は変化があるようだ。 |
葉はヤマブドウ V. coignetiae ,エビヅル V. ficifolia などに比べて薄く、長さ、幅ともに7~5cmほどの偏卵形あるいは偏円形で、3浅裂し、エビヅルのように深く切れ込むようなことはありません。 葉表は展葉直後には薄いクモ毛がありますが、やがて脱落してほぼ無毛となります。 葉裏は若枝同様にはじめ灰白色、のちに淡黄褐色となる綿くずのようなクモ毛がありますが、ヤマブドウやエビヅルほど濃くはなく、生育環境や個体差、時期(展葉からの期間)によっては一見して無毛にみえるような状態のものもあります。 葉脈は葉裏に隆起しており、綿くず状のクモ毛が多いほか、直立した短毛が生えています。
花は5~6月頃に咲き、他の野生のブドウ類と同じく、雌雄異株ですが、「機能上雌雄異株で、他性の器官を痕跡的に併せ持っている」(大橋・門田ほか.2016.p.236)ため、雌花にも雄花より短めで曲がった形状の雄しべがありますが、雌花の花粉は機能しておらず、「花粉もどき」です(星野卓二.2023.牧野富太郎が発見したシラガブドウと新見市利元寺の碑.しぜんしくらしき No.125. p.14-15)。 果実は直径7~10mmほどの球形の液果で、気候にもよりますが8月下旬~9月頃、黒色に熟します。 房は長さ5~12cmほどで、いびつな形状の房も多いエビヅルなどにくらべれば、ブドウの房らしい比較的整った形状のものが多い印象です。 果実は甘酸っぱく、食べることができますが、内部は長さ5mmほどの種子が2~4個入っており、可食部は多くはありません。
 |
 |
| ▲枝には稜角があることが特徴。 稜角は古い枝にも残る。 枝ははじめ灰白色で後に淡黄褐色になる綿くず状のクモ毛が多い。 | ▲雄花序(左)、雌花序(右)。他の野生のブドウ属と同じく「機能上雌雄異株」であり、雌花の雄しべの花粉は機能していない。 |
和名と種小名の「シラガ」は、「白髪」ではなく「白神」で、本種を新種記載した牧野富太郎博士が、本種を見出すきっかけとなった植物講習会の世話人であった阿哲郡上市町(現新見市)出身の植物愛好家、白神寿吉(しらが じゅきち)氏を記念して名付けたものです。 新見市上市の利元寺にある白神氏の墓所には、白神氏を記念した石碑があり、「白神葡萄 Vitis Shiragai Makino 見付け主 名付けの主も年ふりて 共に白髪のおやぢとぞなる。 九十一歳 昭和二十七年正月 牧野結網」と、牧野博士から贈られた言葉が刻まれた石板が埋め込まれています(昭和27年当時、白神氏は数え年で74歳、没年は昭和45年)。 「この碑からは見付け主が白神で、名付け主が牧野であるようにも読み取れる」(星野.2023)のですが、はっきりとした発見の経緯は不明です。 ただ牧野博士は「新見ノ植物講習会ニ臨ム途備中ニ入リテ路傍ノ山足一種ノ葡萄ヲ得タリ」(牧野富太郎.1917.葡萄属ノ一新種.植物研究雑誌.1(4):104-105)と記録しており、新見市への道中に発見・採集したことは確かです。 当時は鉄道が現在の総社市までしか開通していませんでしたので、世話人の白神氏が総社市の駅まで出迎えに行き、同行していた可能性が高いように思われますが、実際にどうであったかは不明です。 少なくとも和名および学名からは、発見のきっかけをつくった人物として、牧野博士が相当の感謝をしていたことがうかがえます。
(2025.5.24 改訂)
 |
 |
| ▲果実は直径7~10mmほど。 内部はほとんど種子で占められており、可食部は少ない。 種子は2~4個あり、長さ5mmほど。 | ▲新見市にある白神寿吉氏の墓地にある石碑。 上部の小型の石板に牧野富太郎博士から白神氏に贈られた言葉が刻まれている。 |