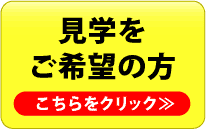おかやまの植物事典
シラン(ラン科) Bletilla striata
環境省第5次レッドリスト(2025):準絶滅危惧 / 岡山県版レッドリスト2025:絶滅危惧Ⅱ類
 |
 |
| ▲当園内に植栽されているシラン。 ランの仲間としては非常に栽培が容易な種類であるため、庭などに良く植栽されている。 | ▲花は背萼片、側花弁、側萼片はほぼ同形。 唇弁は3裂し、左右の裂片は立ち上がる。 中裂片には縦方向の隆起が目立つ。 |
シランは、国内では本州(福島県以南)、四国、九州の日当たりが良く、やや湿り気のある草地や林縁に生育する高さ(花茎の高さ)30~70cmほどの多年草です。 国外では、中国のほか、韓国、ミャンマーなどに分布するとされます〔Flora of China(1994). eFloras (2008). Published on the Internet http://www.efloras.org [accessed 24 April 2025]〕。 岡山県では「吉備高原以南に分布し,日当たりのよい湿地や川岸に生える。」(岡山県野生動植物調査検討会 編,2020.岡山県版レッドデータブック 2020植物編.岡山県環境文化部自然環境課.p.94)とされ、湧水湿地の周囲などでまれに自生と思われる個体に出会うことがあります。
花が美しく、ランの仲間としては栽培が非常に容易な種類であるため広く栽培されており、植栽されたものはよく目にします。 しかしながら、野生個体は開発や植生遷移による自生地の減少に加えて、採集圧などの影響により全国的に減少しているとされ、環境省の第5次レッドリストでは「準絶滅危惧」、岡山県版レッドリスト2025では「絶滅危惧Ⅱ類」とされるレッドデータ植物となっています。 岡山県、とくに南部では植栽された園芸品由来の種子などの飛散によって逸出(逃げ出し)していたり、園芸用土と共に投棄されたものが野生化したと思われるものも多く見られ、真に自生かどうかの判断や、本来の分布域の特定を非常に難しくしています。
 |
 |
| ▲岡山県南東部(備前市)の湧水湿地の周辺に生育していた、野生と思われる個体。 野生個体は非常にまれである。 | ▲葉は長さ20~30cm、幅2~5cmの披針形で両面無毛。 葉脈部分で凸凹に折れ曲がり、筋状になっている。 基部は鞘となる。 |
葉は地際付近の茎から数枚が出て、長さ20~30cm、幅2~5cmの披針形で両面無毛、葉脈部分が凸凹に折れ曲がって筋状になっています。 葉の基部は茎を包んで鞘(しょう)となっています。 花は4~5月頃、花茎の上部にふつう紅紫色の花を3~7個ほどつけます。 花は背萼片、側花弁、側萼片はほぼ同形で長さ2.5~3cm、幅6~8mm、唇弁は3裂していて、中央の裂片は縦方向のひだ状の隆起が目立ちます。 左右の裂片は立ち上がっており、ずい柱が上部を覆うように伸びており、唇弁(+ずい柱)は筒状の形状となっています。
花色はふつう淡紅紫色から濃紅紫色ですが、白花品種 シロバナシラン f. gebina や、唇弁の先端部分のみが、口紅を塗ったように紅紫色を帯びる園芸品種、クチベニシラン cv. kutibeni などがしばしば栽培されています。 なお、クチベニシランについては、かつて倉敷市南部の丘陵地に野生集団が生育していたとの証言があり、当園で栽培している個体は、その野生品由来のものを寄贈されたものです。 クチベニシランは人為的に作出されたものではなく、おそらくは野生の変異個体を園芸品種として栽培するようになったものと考えられます。
 |
 |
| ▲当園で栽培しているクチベニシラン cv. kutibeni 。 現在は園芸品種とされるが、かつては倉敷市南部には自生したという。 | ▲果実は長さ3~4cm、幅1~1.5cm程度の俵形の蒴果。 縦方向に裂開して内部には淡褐色の微細な種子がつまっている。 |
花後には長さ3~4cm、幅1~1.5cm程度の俵形の果実(蒴果)ができます。 先端にはずい柱が宿存しており、晩秋から冬頃に熟して先端が合着したまま縦に裂開し、隙間から長さ1.5~1.8mm程度で淡褐色をした微細な種子を飛散させます。 地下にはやや扁平で横じまのある球状の球茎(偽鱗茎とも)が連なっており、多数の太い根が出ています。
和名を漢字表記すると「紫蘭」で、花が紅紫色であることに由来します。 漢名(中国名)も同じ…と思いきや、漢名は「白及(芨)」(びゃくきゅう)といい、これは地下の球茎を乾燥させたものの生薬名です。 「白及」の由来は、明代の中国の本草学者であった李時珍の著した「本草綱目」によれば、球茎が白く、連及(連なって)して生じることによる、とされます。 また、属の学名 Bletilla (ブレティラ)は、同じラン科の別属 Bletia (ブレティア)属に類似性があることに由来するとされます。 種小名 striata は「縞模様/線状の」という意味のラテン語で、筋のある葉の様子に由来しています。 ちなみにBletia 属の植物はおもに南北アメリカ大陸に分布し、日本には分布しない属で、 Bletia とは、18世紀に南米のペルー・チリの植物調査を行ったスペインの植物学者、イポリト・ルイス・ロペスと、ホセ・アントニオ・パボン・ヒメネスに同行した、同じくスペインの薬剤師、ルイス・ブレ(Luis Blet)氏の名に由来します〔Flora of North America Volume 26: Liliidae: Liliales and Orchidales(2003). eFloras (2008). Published on the Internet http://www.efloras.org [accessed 25 April 2025]〕 。
(2025.4.27)
 |
 |
| ▲地下にはやや扁平で横じまのある球状の球茎(偽鱗茎とも)が連なっている。 球茎は「白及」という生薬で、漢名ともなっている。 | ▲道路の間隙に生育する、栽培品の逸出と思われる個体。 植栽や逸出も多く、自生かどうかの判断や分布域の把握を難しくしている。 |