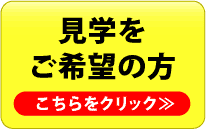おかやまの植物事典
シュンラン(ラン科) Cymbidium goeringii
 |
 |
| ▲元アカマツ林と思われる雑木林の林縁に生育。 日当たりが良く乾燥気味の環境を好み、岡山県では普通種といえるラン。 | ▲葉は長さ20~35cmほどの線形で地際から多数が出て束生。花は3~4月に咲き、その名の通り代表的な春のランである。 |
シュンランは、北海道から九州までの日当たりが良く、乾燥気味のアカマツ林や落葉広葉樹林の林床や林縁に生育する多年生草本です。 国外では、朝鮮半島、中国からブータン、インド北西部地域にまで分布します〔Flora of China(1994). eFloras (2008). Published on the Internet http://www.efloras.org [accessed 27 March 2025]〕 。 岡山県では、南部から北部まで全域に分布しており、かつては中部の吉備高原地域から南部にかけて卓越していたアカマツ林の林床などで比較的普通に生育していたようです。 岡山県ではマツ枯れなどによってアカマツ林が衰退した現在でも個体数は比較的多く、普通種と言えるラン科の植物です。 ただ、岡山県のレッドデータ種となるような状態ではないものの、過去と比較すれば里山の植生変化などによって、開花・結実している個体に出会うことも少なくなっており、生育個体数もだんだんと減少傾向にあると思われます。
 |
 |
| ▲葉(裏面)。 葉脈はやや隆起している。 葉縁には微細な鋸歯があるが、ススキなどのように手を切るようなざらつき方ではない。 | ▲背萼片、側萼片、側花弁は緑色~緑黄色で赤紫色の筋が入る場合もある。 唇弁は白色に濃赤紫色の斑紋がある。 |
葉は柄はなく、地際から多数が出て束生、質は硬く、長さ20~35cm、幅6~10mmほどの線形で葉脈は裏面にやや隆起しています。 葉縁には微細な鋸歯がありますが、葉先から根元に向かって指を滑らすとわずかにざらつく程度で、ススキなどのように手が切れるような鋸歯ではありません。
花は3~4月頃に咲き、高さ10~25cm程度の膜質の鞘状葉に包まれた花茎の先に、普通は花をひとつ着けます。 花は、長さ3~3.5cmほどの直立した背萼片と横方向に腕を広げたような側萼片、やや小型でずい柱(雄しべと雌しべが合着して1本になったもの)にかぶさるように前方に突き出している2枚の側花弁、下向きにカールしている唇弁が組み合わさってできており、背萼片、側萼片、側花弁は緑~緑黄色でしばしば赤紫色の筋が入り、唇弁は白色に濃赤紫色の斑紋があります。 2枚の側花弁に包まれたずい柱の先には白色の葯がありますが、葯は触るとまるで帽子のように外れ(葯帽という)、中から黄色の花粉塊が2つ現れます。 この花粉塊は粘液で覆われており、訪花した昆虫が唇弁にとまり、花の奥に頭を突っ込むと、葯帽が外れ、昆虫の背中に花粉塊がくっ付く仕組みになっています。
花後には長さ6~7cm、幅2cmほどの長楕円形の果実ができ、冬に緑色のまま熟して縦に3裂しますが、果実の先端には萼片が宿存していて、この部分はずっとくっ付いた状態のまま、離れて先端が開くような裂開の仕方はせず、裂開した隙間から微細な種子を飛散させます。 種子は長さ1.5~2mm、幅0.2~0.3mmほどの紡錘形で白色、果実内部に大量に詰まっています。
 |
 |
| ▲ずい柱の先の葯帽を外し、花粉塊を露出させた状態。 写真右よりの唇弁の上にあるのが外した葯帽。 | ▲果実は冬に裂開するが、先端には萼片が宿存しており、この部分が離れて開くことはなく、裂開した隙間から種子を飛散させる。 |
本種の属する Cymbidium(シュンラン)属の植物は、花の美しさ、花の香りの良さから、園芸種として交配など品種改良が盛んに行われており、属の学名の Cymbidium (シンビジウム)は、園芸においても洋ランの園芸種を指す名称としても使われていますが、園芸種の場合は、別属との交配種もシンビジウムと呼んでいる場合があり、園芸における「シンビジウム」と、厳密な意味(植物分類学上)での Cymbidium 属では、指している範囲が異なることに注意が必要です。
和名は「春蘭」で、中国名(漢名)がそのまま和名となっています。 その名の通り、本種は中国においても、日本においても、代表的な春のランとして親しまれてきたことがうかがえます。 同時に本種は非常に別名(地方名含む)が多く、200を超える地方名が知られている(八坂書房 編.2001.日本植物方言集成.八坂書房.p.270-272)ようです。 有名なところでは、唇弁の濃赤紫色の斑紋をホクロ(黒子)に例えたという「ほくろ」、屈曲したずい柱を腰が曲がった老人に例えたという「じじばば」などの別名がありますが、これら別名の由来には諸説あり、「ほくろ」については、「はくり/はっこり/ほーこり/ほくり/ほっくり」などの類似した地方名が全国に分布しています(八坂書房 編.2001)が、それらの地方名は特に「ホクロ(黒子)」を指すものではないようで、斑紋をホクロに例えたと断言するには疑問が残ります。 「じじばば」については、側花弁に覆われたずい柱を、手ぬぐいを姉さんかぶりしたおばあさん、唇弁をひげを生やしたおじいさんに例えたものだとか、唇弁を女性器、ずい柱を男性器または男性そのものに見立て、男性と女性の組み合わせを連想したものと説明される場合もあります。
ちなみに塩漬けのサクラの花にお湯を注いで飲む「桜茶」と同様に、本種の花も塩漬けにして「蘭茶」として飲まれていたとのことですが、現在では花に出会う機会が少なくなっていることもあってか、実際に花を塩漬けにしたり、蘭茶を飲んだことがある人はほとんどいなくなっているようです。(2025.3.29)
 |
 |
| ▲種子は非常に小さく長さ1.5~2mm、幅0.2~0.3mmほどの紡錘形で白色、果実内部に大量に詰まっている。 | ▲塩漬けにした花にお湯を注いで飲む「蘭茶」(写真は塩漬けでなく、生花を使用)。現在ではほとんど飲む機会はなくなっている。 |