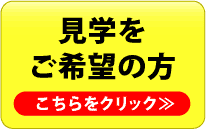おかやまの植物事典
ヤマボウシ(ミズキ科) Cornus kousa subsp. kousa
 |
 |
| ▲日当たりの良い場所を好むが、乾燥は苦手なため、岡山県では降水量の多い中部以北、特に北部の中国山地に多い。 | ▲5月下旬~7月頃にかけて、白い花を咲かせる…が、白い花弁に見えるのは総苞片で、本当の花は中央の球形の部分。 |
ヤマボウシは、本州・四国・九州の山地に生育する、高さ5mから10mあまりになる落葉高木です。 国外では朝鮮半島にも分布します。 国内では、南西諸島(石垣島・西表島)に亜種ヤエヤマヤマボウシ C. kousa subsp. chinensis が分布し、こちらは台湾・中国にも分布しています(大橋広好・門田裕一ほか編.2017.改訂新版 日本の野生植物4.平凡社.p.156)。 森林内でも林縁など比較的明るい場所を好む樹種ですが、そのわりに乾燥は苦手で、ある程度水分条件の良い場所を好みます。 岡山県では、南部でもまれに生育していることがありますが、県中部の吉備高原あたりでは谷筋や北向きの斜面で出会うことが多く、県北部の中国山地など、降水量が多く、冷涼な気候の地域では、自然性の高いブナ林から二次林まで、比較的普通に生育しています。
葉は水平に伸びた枝に対生し、長さ4~12cm、幅3~7cmの楕円形~卵形、葉縁は波打ち、葉脈は表面は凹み、裏面に隆起しています。 表裏とも淡緑色で、表面は無毛かまばらに長軟毛があり、葉裏の葉脈の腋には褐色の毛が密生しています。 花は5月下旬~7月頃にかけて咲きますが、白色の花弁のように見えるのは、葉が変化した「総苞」で、本当の花は4枚の総苞片の中央に位置する直径1cmほどの球形の部分で、多数の小さな花が集まって咲いています。 総苞片は先の尖った卵形あるいは長楕円形で、はじめは淡緑色で小さいですが、開花直前になると白色になり(紅色を帯びるものもあり、品種ベニヤマボウシ f. rosea と呼ばれる)、長さ3~6cmになります。
 |
 |
| ▲葉は長さ4~12cm、幅3~7cmの楕円形~卵形で対生、表裏とも淡緑色。 葉縁は波打ち、脈は表は凹み、裏は隆起している。 | ▲雄性期の花。 花弁は淡黄緑色をしていて4枚。 4本の雄しべが突き出している。 花弁は雄しべとともに脱落する。 |
本当の花には4本の雄しべと1本の雌しべがあり、雄しべが雌しべより先に成熟します(雄性先熟)、 雄性期の花には、よく見ると淡黄緑色の4枚の花弁がありますが、雌しべが成熟する雌性期には雄しべとともに脱落します。 雌しべ(花柱)は雌性期が終わっても果実に残存しています。 果期になると花期には小さく目立たなかった萼筒が肥厚して互いに合着して融合し、ひとつの集合果となり、9~10月頃に赤く熟します。 この果実は甘く、食べることができ、そのまま食用とするほか、ジャムや果実酒として楽しむことができますが、野生個体は枝に手が届かず採取できなかったり、先に野鳥などに食べられて、まとまった量を収穫することはなかなか難しいようです。 果実の中には、硬い殻に包まれた種子(核)が1~数個入っています。
 |
 |
| ▲果期に入りつつある花。 花柱は果期になっても残る。 萼筒の部分は肥厚して合着し一つの果実となる。 | ▲果実は9~10月頃に赤く熟す。 熟した果実は甘く、食べることができる。 果実には1~数個の硬い核が入っている。 |
和名を漢字で表記すると、「山法師」で、「多分丸いつぼみの集まりを坊主頭に、白い総苞をそれの頭巾(ずきん)に見立てたのであろう」(牧野富太郎 著,小野幹雄・大場秀章・西田誠 編.1989.改訂増補 牧野新日本植物図鑑.北隆館.p.494)とされます。 この説明に推測を含めて補足をすると、「山」の部分は「山に生えている」という意味ではなく、白い頭巾をかぶった法師といえば、戦国時代に比叡山(御山)にいた「僧兵」、つまりは「山の法師=僧兵」そのものを指していると思われます。 枝に白い総苞がたくさん見える様子を、白い頭巾をかぶった僧兵の集団をイメージしたものかも知れません。 なお、中国名でもある「四照花」と表記される場合もありますが、中国にも分布するのは亜種ヤエヤマヤマボウシですので、厳密には本(亜)種を指す名ではありません。
![白い頭巾をかぶった僧兵。=「山の法師」が和名の由来か。 高階隆兼 [原画] ほか『春日権現験記繪』巻2,閑野永甫 [ほか4名写],天明4 [1784]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2590961 (参照 2025-05-24)](yamaboushi7.jpg) |
 |
| ▲白い頭巾をかぶった僧兵。=「山の法師」が和名の由来か。 高階隆兼 [原画] ほか『春日権現験記繪』巻2,閑野永甫 [ほか4名写],天明4 [1784]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2590961 (参照 2025-05-24) | ▲植栽されていた常緑の近縁種。 庭木として植栽されることが増えているが、複数の種類が区別されずに流通しているようだ。 |
学名の属名 Cornus (ミズキ属)は、この仲間の材が動物の角のように硬く、剣の柄などに使われたことから、ラテン語で動物の「角」を意味する cornu に由来するとされます(牧野著.小野・大場・西田編.1989.p.1327/豊国秀夫 編.1987.植物学ラテン語辞典.至文堂.p.56)。 本種の材も「かたくて割れにくく、木槌の頭などに使われる」(茂木透ほか著,2000.山渓ハンディ図鑑4 樹に咲く花-離弁花②.山と渓谷社.p.645)とされます。 岡山県北の真庭市蒜山地域の一部では、本種を「うつき」と呼び、「かけや」(大型の木槌)の柄などに利用したとのことです。 「うつき」とは「空木(うつぎ)」のことではなく、「打つ木」の意味だと思われます。 また、種小名 kousa は、ヤマボウシの名所であった箱根で本種が「クサ」と呼ばれていたことに由来するとされます(茂木ほか,2000)。
ちなみに、北アメリカ原産の同属の樹木で、よく植栽されるハナミズキ(花水木) C. florida が、しばしば誤って「アメリカハナミズキ」と表記されることがありますが、在来種の「ハナミズキ」は存在しませんので「アメリカヤマボウシ」とするのが正確です。 また、最近は常緑の近縁種が「常緑ヤマボウシ/トキワヤマボウシ」などと呼ばれ、庭木等として植栽されることが増えていますが、これらは C. hongkongensis や C. capitata (ヒマラヤヤマボウシ)など、複数の種類が区別されずに流通しているようです。
(2025.6.8)