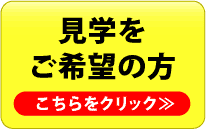おかやまの植物事典
ザクロソウ (ザクロソウ科) Trigastrotheca stricta
 |
 |
| ▲日当たりのよい道ばたや畑地周辺などにごく普通に生育する1年草。 岡山県でも全域に分布する。 | ▲斜上した茎の先にまばらな集散花序をつくる。 雑草的性質の強い植物であり、7~10月頃にかけ随時、発芽・開花・結実する。 |
ザクロソウは本州・四国・九州から琉球列島にかけての道ばたや畑地周辺などの日当たりの良い場所に普通に生育する高さ5~30cm程度の1年草です。 国外では東アジア~インド・太平洋諸島に分布します(大橋広好・門田裕一ほか編.2017.改訂新版 日本の野生植物4.平凡社.p.149)。 岡山県でも畑地雑草などとして、ほぼ全域に分布していますが、近年は、アスファルトやコンクリートの舗装間隙や、都市部の公園などでは、よく似た熱帯アメリカ原産の外来種、クルマバザクロソウ Mollugo verticillata の方が優勢となっているようです。 なお、本種とクルマバザクロソウは、かつてはどちらも同じ Mollugo 属(当時はザクロソウ属)とされていましたが、 2016年に発表された論文(Thulin et al.2016.Phylogeny and generic delimitation in Molluginaceae, new pigment data in Caryophyllales, and the new family Corbichoniaceae.Taxon 65: 784)によって、「科全体の再検討が行われ、従来の属の範囲づけが大幅に変更された」(大橋ほか.2017)ことにより、現在は Mollugo はクルマバザクロソウ属、本種は Trigastrotheca とされ、現在はこちらがザクロソウ属です。 現在、日本にあるザクロソウ属の植物は本種1種のみです。
 |
 |
| ▲花は直径3mmほどで白色。 花弁のように見えるのはがく片で花弁はない。 子房部分は白色(クルマバザクロソウは緑色)。 | ▲果実は球形の蒴果で、熟すと3裂して暗赤褐色の種子が露出する。 種子は円腎形で表面には細かな突起がある。 |
雑草的性質の強い植物であり、7~10月頃にかけて随時、発芽・開花・結実します。 花は直径3mmほどで白色、斜上した茎の先にまばらな集散状花序をつくって咲きます。 なお、5枚の花弁のように見えるものはがく片で、花弁はありません。 開花は午前中ですが、本種の花は11時前にはしぼんでしまう場合が多く、対してクルマバザクロソウの花はもう少し遅くまで開花している傾向があるようです。 また、本種は子房の部分も白色ですが、クルマバザクロソウの子房は緑色をしています。 果実は球形の蒴果で、熟すと3裂して種子が露出し、落下することで散布されます。 種子は直径0.5mm程度の腎円形で暗赤褐色をしています。 種子の表面には細かな突起がありますが、ルーペでは観察が難しいので、実体顕微鏡などで観察する方が良いでしょう。
 |
 |
| ▲茎は細く、稜(角張った部分)がある。 よく似たクルマバザクロソウの茎は丸くて稜がなく、両種の良い区別点である。 | ▲葉は長さ1.5~5cmの披針形~倒披針形、3~5枚が偽輪生する。 クルマバザクロソウの葉は本種よりやや多く4~7枚。 |
茎は地際から何本かの茎が分枝して斜上(斜めに立ち上がる)しますが、茎には稜(角張った部分)があります。 クルマバザクロソウの茎には稜がなく、両種の区別点のひとつとなりますが、茎の先、花序軸などでは稜が目立たない場合がありますので、観察する場合には地際付近の比較的太い茎を観察すると分かりやすいかと思います。 葉は長さ1.5~5cmの披針形~倒披針形で、茎の分岐や花序の付け根に3~5枚が偽輪生(葉の着く位置がつまって輪生のようにみえる)しています。 クルマバザクロソウは茎があまり斜上せず地面に張り付くように広がり、葉は長さ1~3cmほどの倒披針形で本種よりやや小さく、4~7枚が偽輪生しますが、葉の数、形状、大きさなどは生育環境などによって変化が大きいため、見分ける際には多少注意が必要です。
 |
 |
| ▲熱帯アメリカ原産の外来種、クルマバザクロソウ Mollugo verticillata 。 以前は本種と共にザクロソウ属とされていた。 | ▲樹木のザクロ(ミソハギ科)の果実(左)と葉(右)。 牧野富太郎博士は葉が似ていることを本種の名の由来としているが・・・。 |
和名は「柘榴(石榴)・草」で、日本でも平安時代ごろから栽培されているミソハギ科の樹木、ザクロ Punica granatumに由来するようです。 ただし、ザクロソウの名が書物に登場するのは、江戸時代後期の1825年に刊行された「物品識名拾遺」が初出とされ(磯野直秀.2009.資料別・草木名初見リスト.慶応義塾大学日吉紀要・自然科学.No.45:p.69-94) 、ザクロソウの名は比較的新しい名のようです。 おそらく、それ以前には中国名である「粟米草」の名がそのまま使われていたのではないかと考えられます。 牧野富太郎博士は、「其葉状ざくろ葉ニ類スレバ斯ク言フ」(牧野富太郎.1940.牧野日本植物図鑑.北隆館.p.604)と、本種の葉が質感、形状がザクロを思わせることを由来としており、現在の多くの植物図鑑でも、牧野博士の説に従うかたちで、葉が似ていることが和名の由来、としています。 確かに、葉脈が目立たず、無毛でやや質が厚くみえる葉の様子は、ザクロの葉に似ていますが、本種の裂開した蒴果に暗赤褐色の種子が入っている様子も、裂開したザクロの果実内部の赤い仮種皮に覆われた種子が見えている様子に似ています。 葉だけではなく、果実などの様子もあわせて、ザクロソウと呼ばれるようになった…と考えるほうが説得力があるように思われます。
属の学名 Trigastrotheca はラテン語で「3」を意味する trias + 「腹」を意味する gaster + 「箱・包み」を意味する theca (田中秀央 編.1952.羅和辞典.研究社.p.647,263,631)を組み合わせた名と考えられ、子房が3室に分かれていることを意味する名のようです。 種小名 stricta は、「直立」を意味するラテン語 strictus が由来(豊国秀夫 編.1987.植物学ラテン語辞典.至文堂.p.191)で、本種の茎が立ち上がることを表していると考えられます。