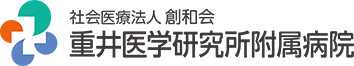血液浄化療法センター

当院は県内で最初に人工透析を始めたしげい 病院と同一法人(社会医療法人創和会)の病院です。慢性腎臓病は新たな国民病とも言われ、透析治療を受ける患者さんは国内で34万人を超え、岡山県でも約5,000人の透析患者さんがおられます。その約5,000人のうち約15%の方が創和会の2つの病院で治療を受けています。
当院では腎機能や患者さんのライフスタイルに応じた、さまざまな血液透析・腹膜透析を提供しており、小児から成人までの腎臓病を幅広く診察をしています。また、心肺機能の強化をはかり、 筋力を増強することで、合併症の症状が改善するように、腎臓リハビリテーションも行なっています。
当院では腎機能や患者さんのライフスタイルに応じた、さまざまな血液透析・腹膜透析を提供しており、小児から成人までの腎臓病を幅広く診察をしています。また、心肺機能の強化をはかり、 筋力を増強することで、合併症の症状が改善するように、腎臓リハビリテーションも行なっています。
現在は、COVID-19に対応した病床を確保して 新型コロナウイルスに感染した透析患者さんの 治療も行なっております。
2020年当院の腎臓内科では、外来患者677名、 入院患者197名、外来血液透析患者389名、腹膜透 析10名の診療を行いました。また、外科では透析シャント拡張術(PTA)1,071例、膜透析関連手術・ バスキュラーアクセス手術247例を行っています。
この数多くの患者さんの治療を支えているのが、透析に関わる内科医(8名)、消化器内科医(4名)、外科医(2名)です。診療科の垣根を越えて院内全体で慢性腎臓病の患者さんの治療にあたっています。また、血液浄化療法センターの看護師と臨床工学技士、薬剤師、管理栄養士、リハビリスタッフ、事務職員等、院内の各職種のスタッフが、患者さんの自分らしい生活を支えられるように治療を行っています。
2020年当院の腎臓内科では、外来患者677名、 入院患者197名、外来血液透析患者389名、腹膜透 析10名の診療を行いました。また、外科では透析シャント拡張術(PTA)1,071例、膜透析関連手術・ バスキュラーアクセス手術247例を行っています。
この数多くの患者さんの治療を支えているのが、透析に関わる内科医(8名)、消化器内科医(4名)、外科医(2名)です。診療科の垣根を越えて院内全体で慢性腎臓病の患者さんの治療にあたっています。また、血液浄化療法センターの看護師と臨床工学技士、薬剤師、管理栄養士、リハビリスタッフ、事務職員等、院内の各職種のスタッフが、患者さんの自分らしい生活を支えられるように治療を行っています。
施設認定
- 日本腎臓学会腎臓専門医制度研修施設
- 日本透析医学会専門医制度認定施設
- 日本腎臓財団透析療法従事職員研修実習指定施設